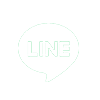1. なぜ製造業での労災被害が多いのか?
兵庫県内における労働災害の死傷者数は、製造業が最も多いという統計データがあります(兵庫労働局『令和7年(1月~7月)労働災害の発生状況』)。
製造業の次は陸上貨物運送業、その次が建設業となっています。
ただ、令和7年に生じた「休業4日以上の死傷災害」によると、令和6年と比べると全体として(2509人→2413人)とわずかに減少しており、製造業での事故も(548人→571人)になり、やや減少傾向にあると言えます。
2. よくある事故パターンとその原因
製造業においてよくある事故のパターンとしては、機械への「はさまれ、巻き込まれ」によるものが最も多く、次いで、「転倒」による怪我が多くなっています。
他には、「動作の反動・無理な動作」による怪我、「墜落・転落」による怪我、「飛来・落下」による怪我、「高温・低温の物との接触」による怪我などがあります。
死亡事案には、「墜落・転落」によるもの、「巻き込まれ・はさまれ」によるもの、「高温・低温の物との接触」によるもの、「有害物等との接触」によるものがあります。
では、どのようなことが原因で労災事故は起こるのでしょうか?
そもそも製造業は、機械設備を利用する作業が多いことから、労働災害が起こりやすい環境にあると言えます。
直接の原因としては、さまざまな要因が考えられるのですが、まずは労働者側の不注意や疲労・理解力不足による操作ミスがあげられます。しかしながらその背景には、会社側の過重労働や安全教育が不十分であることが多いです。
機械自体の不具合であったり、安全装置が設置されていないといった原因もあります。
照明が暗かったり、通路に物が置かれていて通りにくかったり、床や階段が滑りやすかったりと言った作業環境が良くないことも考えられます。
複数の原因が絡み合って重大な労災事故を引き起こしているケースもあります。
3. 労災申請・補償制度の概要
製造業での作業従事中に労災事故にあってしまった場合は、まずは、必ず労災申請をしてください。
労災事故が労災認定されれば、治療費が労災保険から全額支給されますし、休業している期間は給与の約8割が支給されます。
そうすれば、焦ることなく安心して治療に専念できます。
労災申請のやり方としては、次のような順番で労働者の方本人が行うことになります。
1. 労災保険給付支給請求書を作成する
2. ➀を労働基準監督署長宛に提出する
3. 労働基準監督署が労災に該当するかどうかを審査する
4. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
5. 支給の決定があれば、厚生労働省より労災保険給付が行われる
上記の作業は、給付の内容ごとに行う必要があります。
ちなみに労災保険には、次のような補償制度があります。
1. 療養補償給付・療養給付
労働災害による傷病が治癒するまで、療養を無料で受けられる制度です。
2. 休業補償給付・休業給付
労働災害による傷病で休業した場合には賃金が得られないため、支給されるものです。
3. 傷病補償年金・傷病年金
労働災害による傷病の療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当する場合に支給されるものです。
4. 障害補償給付・障害給付
労働災害による傷病によって、身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。
5. 遺族補償給付・遺族給付
労働災害によって死亡した場合に遺族に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類あります。
6. 葬祭料・葬祭給付
労災によって死亡した場合に、葬祭を行った者に支給されるものです。
7. 介護保障給付・介護給付
傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給されるものです。
8. 二次健診段等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常が見られた場合に、受けることができるものです。
この中でも④の後遺障害等級の認定は、認定されるかどうかで大きく金額が違ってきますので、重要なものとなってきます。
4. 労災保険だけで不十分なケースとは?
実は、労災保険だけでは補償が不十分なケースがあります。
つまり、労災保険から支払われるのは、本来受けられる補償の一部にすぎないことがあるのです。
特に、労災によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険では給付されません。
労災保険で不十分な補償の部分については、別途、事業主に対して損害賠償請求をする必要があります。
労災保険が支払われたことで満足している場合ではないかもしれないのです。
5. 損害賠償請求の可能性と安全配慮義務
では、事業主に対して損害賠償を行える可能性がある場合について説明します。
事業主は、雇用契約を締結している労働者に対し、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。
この安全配慮義務の「違反」が認められるのであれば、損害賠償請求が可能となります。
例えば、製造業に関して言うと、事業主側で製造機械の利用に関する指導や教育を行ったり、製造機械の定期検査等のメンテナンスを行ったり必要があるのに、実際には十分な対策を怠っていた、それによって労災が発生したような場合には、安全配慮義務違反が認められると言えます。
6. 弁護士に相談すべきケースとは?
実際に労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
具体的には、請求できる損害を請求し忘れたり、金額が過少であったりするなど、本来得られたはずの給付が得られなくなる恐れがあるのです。
この点、弁護士に相談しておくことで、本来受けられるべき補償内容がわかり、適切な金額を事業主に請求することが可能となります。
もちろん後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることが可能となります。前述しましたが、後遺障害等級の認定次第で受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントとなってきます。
弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として手続きを行ってくれるため、煩雑な手続きから解放され、職場復帰に向けて治療やリハビリに専念できることにもなります
相談を受け、正確な知識を持っておくだけでも、十分意味があります。
また、仮に示談交渉が難航し、裁判に移行せざるを得ないような場合でも弁護士が対応します。
弁護士に依頼することで訴訟に対する精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能になるでしょう。
7. 当事務所のサポートの内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。
一人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
お気軽にご相談にいらしていただければと思います。
初回
相談料0円
- 労働災害の無料相談
- 050-5451-7981
- 平日・土日9:00~20:00