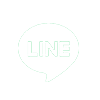- 後藤 千絵
- 京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。
目次
労災を弁護士に依頼するメリット
<パターンA>
①「代理人」として会社(事業主)と直接交渉ができる
弁護士は、あなたの代わりに代理人として交渉を行うことができます。この点、社労士は代理人として、会社(事業主)との交渉をすることができません。
会社(事業主)との交渉は、勤務中であっても退職後であっても、一般の方にとってはかなりの負担となってきます。しかも法的な争点になってくると、専門的な法的知識や交渉能力、経験値が必要になります。交渉の仕方によっては、得られる金額に差がでることも十分あり得ることです。
このため、労災により怪我をされた場合には、早い段階で弁護士に依頼し、代理人として会社と交渉を行ってもらうことをお勧めします。
②後遺障害認定に強い
後遺障害の認定を受けるためには医師からの診断書が必須になります。しかしながら、医師の作成した診断書の記載内容によっては、本来であれば認定を受けることができた後遺障害なのに、認定をうけることができなかったといったケースも散見されます。このため、後遺障害の認定に強い弁護士に依頼をし、医師への対応の仕方等のアドバイスを行ってもらうことで、適切な後遺障害の認定を勝ち取ることが可能となってきます。後遺障害認定を受けることができれば、会社(事業主)に対して適正な損害賠償請求ができる可能性も高まります。
ぜひ早期に弁護士に相談をし、どのようにしたら後遺障害認定を受けることができるのか、適切なアドバイスを受けてください。
③労災申請のみならず、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能になる
労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。
これとは別に、逸失利益や慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士は代理人として、労働審判や民事訴訟等の方法により会社(事業者)に対し損害賠償請求が可能です。
労働審判を選択するのか、または民事訴訟なのか、交渉で解決すべき事案なのか、この点についても経験豊富な弁護士であれば適切に判断することが可能です。
適切な救済手段が何かを含め、ぜひ弁護士にご相談ください。
<パターンB>
労災保険の申請をサポート
労働災害事故によって負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。
ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。
その理由の多くは、①労災保険の保険料を払っていない(労災保険に加入していない)、②申請手続が面倒である、③労基署からの調査や行政処分を恐れている、④工事の受注に影響する、と言ったもっぱら会社側の都合によるものです。
労災保険への加入は会社(事業主)の義務ですが、仮に会社(事業主)がこの義務を怠って労災保険の加入をしていなくても(➀のケース)、労働者は労災保険を使うことが可能なのです(申請があれば給付を受けることが可能です)。
労災保険の申請は労働者の権利であり、②③④のような理由で会社(事業主)が申請を拒否することは許されません。
労災隠しなど会社(事業主)が申請に非協力的な態度を示したら、すぐに弁護士にご相談ください。何度も言いますが、会社(事業主)の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能なのです。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。
会社(事業主)への損害賠償請求をサポート
労災事故が発生した場合、会社(事業主)に過失があってもなくても、労働者は労災保険からの給付を受けることができます。
労災保険は会社(事業主)に落ち度がなくても、業務中の事故による負傷等であれば一定額を労働者に給付するもので、労働者にとって貴重な制度です。
ただ、労災保険は国が定めた制度として、いわば最低限の補償給付を行うものでしかありません。
つまり、労災保険では給付されない労働者の損害があるのです。
例えば、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②事故前収入の100%分の休業補償などです。
労災事故の発生について、会社(事業主)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②100%分の休業損害の各賠償請求を会社(事業主)に対して行うことができます。
~参照 労災事故の損害賠償請求におけるポイント
仮に労災事故が自身のミスに起因するものであった場合、あるいは他従業員の操作ミス等によって起こったものである場合、会社(事業主)に責任があるのか?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社(事業主)には「安全配慮義務」という労働者が安全に労働できる環境を整備すべき義務があります。
会社(事業主)がこの義務に違反した場合、その結果生じた労災事故による労働者の損害を賠償しなければならないのです。ですので、仮に自分のミスがあったとしても、会社(事業主)に安全配慮義務違反があるならば、会社に対して損害賠償請求することは可能なのです。
また、他従業員の過失行為によって生じた損害については、その従業員の使用者である会社(事業主)も賠償しなければならないのです。
そのため、世の中の労災事故のうち、労災保険による補償給付を受けるだけでは、実は本来受けるべき補償を十分に受けられていないというケースが相当多くあるのです。
とはいえ、これまでお世話になっていた会社(事業主)に対し、労働者個人が請求や交渉をすることはとても勇気のいることですし、自信がないという方も多いでしょう。 そこで、経験豊富な弁護士が事故内容を把握し、請求の可否の検討をした上で、会社(事業主)への請求・交渉を代理人として行います。弁護士が会社への損害賠償を全面的にサポートするのです。
治療中からのサポート
労災事故による負傷後、精一杯の治療を続けたとしても、残念ながら完全には治らないというケースがあります。
例えば、身体に麻痺が残った、身体に欠損が生じた、関節の可動域が狭まった、痛みやしびれが続いている、などの場合です。
このような場合、主治医に障害給付請求用の診断書を作成してもらい、身体の不具合を後遺障害として、労基署に認定してもらうことになります。
労災保険からの給付金にしても、会社(事業主)からの賠償金にしても、この後遺障害の認定等級(1級から14級、非該当)によって金額の多寡が大きく左右されることになります。
そのため、適正な金額を受け取るためには、この後遺障害等級の認定が極めて重要になるのです。
そして、この適正な後遺障害等級認定結果を得るためには、しかるべきタイミングで、適切な医療機関で適切な治療を受け、適切な画像所見(MRI、CT等)を受けておく必要があります。
そのためには、一定の医学的知識を有し、人身傷害分野(労災事故、交通事故等)の経験を積んでいる弁護士から、治療中のアドバイスを受けることが後遺障害の認定にとって極めて有利になってきます。
当事務所では、治療中の段階から、被災労働者の方からのご相談に応じ、適時に適切なアドバイスをさせていただくよう努めております。
初回
相談料0円
- 労働災害の無料相談
- 050-5451-7981
- 平日・土日9:00~20:00